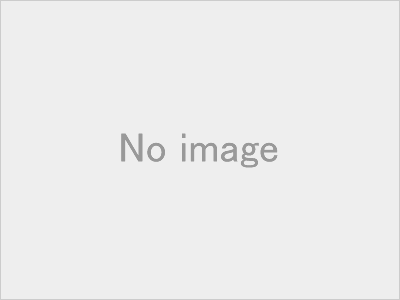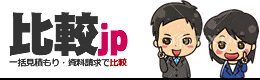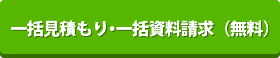監修者
目次
ホームページを立ち上げるとき、「まず何から始めればいいの?」と迷う企業は少なくありません。社内に専門知識がなくても、おおまかな目的やサイトのイメージをまとめておくだけで、制作会社との話し合いがスムーズになります。本記事では、ホームページ制作における仕様書の大切さと、抑えておきたい基本ポイントを分かりやすくご紹介します。
ホームページ制作の仕様書が果たす役割
ホームページを作るにあたっては、サイトの見た目や機能をしっかり言語化しておくことが大切です。ここでは、仕様書がなぜ重要なのか、どんな役割を持っているのかを分かりやすく紹介します。専門知識がない方にも理解していただけるよう、基本の考え方からメリットまでを順序立てて説明していきます。
ホームページ制作の仕様書とは
ホームページ制作の仕様書は、どんなデザインにしたいか、どんな機能を導入したいか、運用をどのように行うかなどを文章化して整理したものです。
制作を依頼する企業と受注する制作会社の間で「こういうサイトを目指している」というイメージを共有しやすくなり、社内でも方針が明確になります。たとえ専門的な知識がなくても、この仕様書を見るだけでサイトの仕上がりをイメージできる点が大きなメリットです。
なぜ仕様書が必要なのか
ホームページ制作では、担当者同士の認識が意図せずズレたり、公開間際に大きな修正が必要になったりすることがあります。ですが、初めの段階で仕様書を準備しておくと「どんなデザインにしたいか」「どこに何を配置するか」が明確になり、思わぬトラブルを減らせます。
特にページ数が多いサイトや、複数の部署が関わる場合は、仕様書のおかげで全体を把握しやすくなり、無駄な作業のやり直しを防ぎやすくなるでしょう。
要件定義書との違い
要件定義書は、主にシステム開発の現場で使われることが多く、実装すべき機能や動作の仕組みを中心にまとめています。一方で、ホームページ制作の仕様書はページの配置や色づかい、運用担当者の決定など、より具体的なデザイン面や管理面にまで踏み込むのが特徴です。
もちろん両方を連携させたほうが精度は高くなりますが、ホームページ制作の仕様書は「実際の見た目や操作感」に重きを置いている点が大きな違いです。
また、 要件定義書は多くの場合、発注側が中心となって作り上げ、制作会社がどのような提案や要件を具体化するかを考える際の重要な資料として使われます。
仕様書を作成する3つのメリット
ホームページ制作の仕様書には、完成後のサイトの姿や運用管理の方法を明確にする役割があります。ここからは、仕様書を用意することで具体的にどのようなメリットが得られるのかを見ていきましょう。
依頼内容を体系的にまとめられる
仕様書を作ると、デザイン面や機能面、サイトに載せる情報などを一つひとつ整理できるため、全体的な方向性が明確になります。
たとえば、トップページでは会社の特徴を強く打ち出すのか、それとも商品やサービスの一覧を優先して配置するのか、といった優先順位を検討しやすくなるでしょう。
こうして仕様書の段階で細部まで詰めておくと、追加で見積もりが必要な項目やスケジュールに影響が出そうな工程を早めに把握でき、「思っていたより費用や時間がかかる」という事態を減らせます。
修正依頼がスムーズ
制作の途中で色合いを変更したい、文章を変えたいといった要望が出てきたときも、あらかじめ合意されている仕様書があれば、どの部分をどう直すかをすぐに特定できます。必要な情報が一つにまとまっているので、制作会社とのやり取りがスピーディーになり、大幅な手戻りが起こりにくくなります。
担当者間の連携が円滑になる
企業の担当者が変わっても、仕様書を引き継げばプロジェクトの現状や目標をすぐに把握できます。制作会社側も新しい担当者に改めて一から説明する手間が減るため、お互いのコミュニケーションが円滑になるでしょう。結果として、公開までの時間を短縮しやすくなります。
コストや予算の見通しが立ちやすい
仕様書に必要な機能やページ構成を詳しく書いておくと、制作の範囲が明確になるため、見積もりや予算計画を立てやすくなります。曖昧なまま進行してしまうと、後から「これも追加したい」「あれも必要だった」というように費用が膨らむケースが出やすいですが、最初に仕様書で要件を固めておけば想定外の支出を抑えられるでしょう。
仕様書に盛り込むべき4つのポイント
前の章では、ホームページ制作における仕様書のメリットを紹介しました。では具体的に、どのような内容を仕様書に含めれば、サイトの完成度や制作工程のスムーズさを高められるのでしょうか。
ここでは、特に押さえておきたい4つの項目を解説します。
プロジェクトの概要
まず必要なのが「プロジェクト概要」です。これはホームページ制作の基本方針や目標をはっきりさせるためにまとめておくもので、サイトづくりの核になる部分です。以下の項目を整理しておけば、制作途中で意見がぶれたり、認識のズレが起きたりするリスクを減らせます。
- サイトの名称(プロジェクト名)
- 使用するドメイン(URL)
- 制作の目的や背景
- ターゲット
- 抱えている課題や問題点
- 達成したい問い合わせ数やアクセス数
- リリース予定日(公開日)
たとえば「製品をもっと多くの人に知ってもらいたい」「採用向けに会社の魅力を強調したい」といったゴールを言語化しておくと、デザインの方向性や必要な機能を考えやすくなります。複数のゴールがある場合も優先度を決めておくと、制作会社との調整がスムーズです。また、どのユーザー層に向けて発信するかを意識しておくと、写真や動画の使い方、テキストの量などを明確にしやすくなります。SNSや検索エンジンをどう活用するかの方針があるなら、ここに合わせて記載しておくと良いでしょう。
スケジュール表
どの段階でどんな作業を行うかを明確にすることは、プロジェクトの円滑な進行に欠かせません。
一般的には、要件定義やデザイン、コーディング、テスト、公開といった工程ごとに期間を区切り、公開予定日から逆算してスケジュールを組むことが多いです。社内で承認が必要なタイミングや、デザインの確認にかかる日数を余裕を持って盛り込み、それぞれの工程が遅れた場合のバッファ(余裕時間)を検討しておけば、最終的な納期に影響しにくくなります。特に、依頼者側がデザインや原稿を早めに用意する必要がある場合は、社内体制をどう整備するかも視野に入れてスケジュール表を組むと、予想外のトラブルを防ぎやすいです。
| 工程 | 内容の例 | 目安期間 |
|---|---|---|
| 要件定義 | サイトの目的、ターゲット、機能の洗い出し | 1~2週間程度 |
| デザイン | ワイヤーフレームの作成やページデザインの検討 | 2~3週間程度 |
| コーディング | HTML/CSS/JSなどでの実装、および動作確認 | 2~4週間程度 |
| テスト | 不具合の洗い出しやブラウザチェック、修正対応など | 1~2週間程度 |
| 公開 | サーバーへのアップロードや最終確認 | 1週間程度 |
作業内容によってはこの表よりも短縮できる場合や、逆に時間がかかる場合もあるため、社内外の関係者とスケジュールをすり合わせながら調整していきましょう。
サイトマップ
サイトマップを作ることで、ホームページ全体がどのように構成されているのかを一目で把握できます。
たとえば、トップページから商品紹介ページやお問い合わせフォームにどのようにつながっていくか、コンテンツ同士のリンク関係がどうなっているかなどを整理しやすくなります。サイトマップがしっかり作られていれば、閲覧者が迷わず目的の情報にたどり着ける設計がしやすくなるほか、無駄なページや重複したコンテンツを減らすことも可能です。また、後から新しいページを追加したいときも、既存の構成との整合性を取りやすいという利点があります。
ワイヤーフレーム
実際のデザインに入る前段階で、ページ全体のレイアウトや要素の優先度を視覚化するのがワイヤーフレームの役割です。
たとえば、トップページのメインビジュアルを大きく配置するのか、それともすぐに製品一覧に誘導する導線を設けるのかなど、ビジネス上の狙いを形にしやすくなります。ワイヤーフレーム段階で制作会社と認識を合わせておくと、いざデザインを仕上げる段階で「思っていた配置と違う」などの食い違いが起きにくくなるでしょう。
加えて、配置するテキストや画像の量を早めに把握できるため、撮影や文章制作などの準備を計画的に進められる点も、大きなメリットです。
仕様書を作成する際の要注意事項
ここからは、制作が進むうえで見落としがちな注意点を整理していきます。事前に仕様書へ反映しておくだけで、トラブルを防ぐ効果が高まるはずです。
スマホ対応・ブラウザ対応、OS要件
現在はスマホやタブレット、パソコンなど、さまざまな端末でホームページが閲覧されます。どのOSやブラウザのバージョンまで対応するか、正しく動作するデザインや機能はどこまで確認するかを仕様書で明記しておくと安心です。
とくにモバイルユーザーが多い場合は、レイアウト崩れや読み込み速度などにも注意が必要になります。
SSL化について
個人情報や決済情報を扱う場合や、セキュリティを強化したいときは、SSL(Secure Sockets Layer)による通信の暗号化を検討しましょう。
仕様書の段階で導入の有無を決めておくと、リリース直前であわてるリスクを減らせます。検索エンジン対策の面でも、SSL化しているサイトのほうが評価されやすい傾向にあります。
サーバー・ドメインの対応(納品形式)
公開先となるサーバーをどこが用意するのか、既存ドメインを引き継ぐのか、新規ドメインを取得するのかなど、運用面を含めて仕様書に明記しましょう。
最終的にどの形式で納品するかも決まっていれば、制作会社と発注側の連携がスムーズに進みます。
支払方法について
制作費用の支払方法やスケジュールを事前に決めておくと、後からのトラブルを防げます。振込や支払期日など、利用できる支払い手段がどれなのか、分割払いが可能かどうかなどを仕様書に書き込んでおくと、契約上の手戻りを減らせるでしょう。
原稿・素材の準備について
ホームページに掲載する文章や画像、動画などを誰が用意するのか、いつまでに準備すべきかを明確にします。制作途中で「必要な素材がそろっていない」となるとスケジュールにも影響が出やすいので、担当部署や数量などを事前に確認しておきましょう。
公開作業の担当について
サーバーへのアップロードやドメイン設定などの作業を、どちらの担当者が行うかを決めておくと、直前での混乱を防げます。専門知識が必要なケースが多いため、制作会社と発注側の役割分担をしっかり仕様書に落とし込みましょう。
運用・保守について
サイトの公開後も、定期的な更新やセキュリティ対応、場合によっては機能追加などが必要です。社内で対処できることと制作会社に依頼することを明確にしておくと、余計なやり取りを減らせます。特にセキュリティ面で不測の事態が起きた場合、どのように対処するかを事前に取り決めておくと安心です。
アクセシビリティ対応
ユーザーによっては、視覚や聴覚、操作面に制限があることも想定されます。音声読み上げ機能に対応しやすい設計や、キーボードのみで操作できる導線づくりなど、アクセシビリティ基準(JISやWCAG)のどこまでを考慮するかを仕様書に明記しておくと、多様な利用者に配慮したサイトを実現しやすくなります。
仕様書作成を成功させるための視点
前の章では、ホームページ制作における注意事項を紹介しました。そこで挙げたポイントを踏まえつつ、仕様書の完成度をさらに高めるための視点を解説します。
最終的なクオリティやスムーズな進行は、制作開始前の準備によって大きく左右されるため、ぜひ参考にしてみてください。
社内の意見を幅広く取り入れる
ホームページの制作目標や機能要件などは、部署ごとに異なる優先度を持っている場合があります。
たとえば営業部門なら「問い合わせフォームを強化したい」、広報部門なら「最新情報を発信しやすい仕組みが欲しい」といった具合です。担当者だけでなく、関連部署の担当者をドラフト段階から巻き込み、必要な意見を反映していくことで、後からの大幅な修正や抜け漏れを防ぎやすくなります。
可能な限り項目を埋める
仕様書はサイトの青写真ともいえる重要な資料です。大まかにしか書いていないと、あとで「これを書いていなかった」という問題が発生する可能性があります。小さな内容であっても最初に洗い出しておくと、制作会社とのやり取りや社内承認の手間を減らすことができます。
特にフォームの仕様やページの文言など、細かい部分ほど最初からリストアップしておくと安心です。
制作会社に依頼する範囲を明確にする
サイトデザインやプログラム開発、原稿のライティングなど、どこまでを制作会社に任せるのかは明確に決めておきましょう。曖昧なままプロジェクトを進めると、見積もりや納期でトラブルが発生する場合があります。契約時点で担当領域をしっかり定義しておけば、費用やスケジュール管理がしやすくなり、お互いの負担も軽くなります。
公開後の運用や保守を想定しておく
ホームページは公開して終わりではなく、情報の更新やセキュリティ対策などが今後も発生します。仕様書を作成する段階で、更新頻度や管理方法を決めておくと、公開後の運営がスムーズに進むでしょう。
担当者を社内で割り振るのか、それとも制作会社に継続的な保守を依頼するのかといった点も、事前に話し合っておくことで、予想外のトラブルやコスト増を防げます。
比較jpはホームページ制作に関する一括見積もりの比較サイトです
比較jpはホームページの制作に関する要望などを一度ご入力いただくだけで複数の業者に一括で見積もり依頼を行うことができます。
届いた見積もりや提案などを比較するだけで、制作費用はもちろん、制作スピートやデザインセンス、担当者の対応、集客に関する提案力など制作会社を様々な面から比較し探すことができます。
もちろん見積もり依頼は何度ご利用いただいても無料!
詳しくは「ホームページ制作会社を比較」のページにてご確認いただけます。
依頼実績一覧
ホームページ制作会社を検索
ホームページ制作に関するコラム
WordPressとは?無料ブログとの違い?メリット・デメリット9選
WordPressのホームページ制作相場とは?費用の内訳とコストを抑えるポイント
ポータルサイトとは?種類やメリット・デメリット、制作・運営する際の注意点
ホームページリニューアル完全ガイド|メリット・失敗する原因・手順
キュレーションサイトの仕組みとは?種類・メリット・注意点を解説
オウンドメディアとは?メリット・デメリット・成功事例まで徹底解説
ネイルサロンのホームページ制作|競合他社と差をつける要素や必要なコンテンツ
ホームページ制作会社の選び方7選|失敗しないための注意点とポイント
最低限知っておくべきアナリティクス(Analytics)の使い方(基本中の基本編)
CMSとは?CMSの種類や知っておくべきメリット・デメリット
フリーランスにホームページ制作を依頼するメリット・デメリットと費用相場を解説
ホームページ制作を外注するメリット・デメリット!費用を安く抑える方法も解説
失敗しないレンタルサーバーの選び方|料金・性能・サポートで選ぶ最適なサーバーとは?
ホームページ制作会社の種類を得意分野別・規模別・料金体系別に紹介
「格安ホームページ制作」の落とし穴!安さに隠れたリスクや注意点
アクセシビリティとは?求められる背景やメリット、デメリットについて
ホームページ制作ツール完全ガイド|初心者でも使える無料ツール13選
ホームページ制作の見積もりが高い?内訳の相場や注意点について
既存ホームページのCMS化(WordPress化)とは?メリット・デメリットについて
グループウェアと社内ポータル、社内Wiki、社内SNS、社内掲示板の違いとは?
ホームページ制作の仕様書とは?メリット・基本ポイント・注意点をわかりやすく解説
ホームページ制作の納期は?期間の目安や工程別スケジュール、短縮するコツについて
ホームページ制作契約書の基礎知識|トラブル回避に役立つ必須項目
小学校・中学校・高等学校のホームページ制作会社の選び方と制作費用相場
小学校・中学校・高等学校に強いおすすめホームページ制作会社5選
学習塾・予備校のホームページ制作の費用相場と制作会社の選び方
学習塾・予備校のホームページ制作完全ガイド|集客・費用・失敗例まで徹底解説
契約書・要求定義書・要件定義書・企画提案書・見積書・仕様書の違い
研究室ホームページの制作費用の相場と実績が豊富な制作会社6選
大学・短大ホームページの制作費用相場と制作実績が豊富な制作会社5選


ホームページ制作会社を比較できるビジネスマッチングサイト
比較jpは ホームページ制作、ECサイト制作、ランディングページ制作、スマホサイト制作、Facebookページ制作 など様々な分野について一括見積もりや資料請求依頼が無料で行えます。

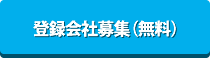
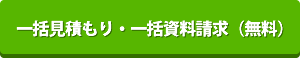

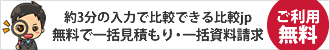
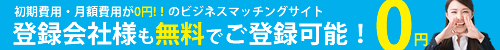



 拡大する
拡大する 拡大する
拡大する