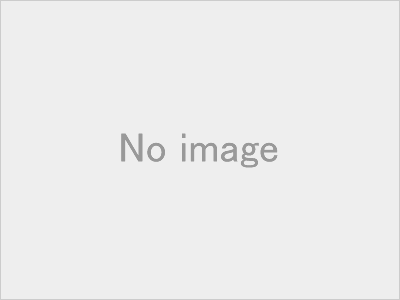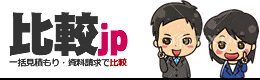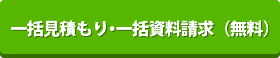監修者
監修者
目次
ホームページを作るとき、デザインや機能にこだわるのは当然ですが、「アクセシビリティ」について考えたことはありますか? これは、年齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が快適に利用できるウェブサイトを作るための大切な要素です。実は、アクセシビリティに配慮することで、ユーザー満足度が向上するなど、多くのメリットがあります。しかし、その一方で、コストや制作期間に影響を与えるなどのデメリットもあります。
この記事では、アクセシビリティの重要性や対応方法について、分かりやすく解説していきます。
ホームページのアクセシビリティとは?
ホームページのアクセシビリティとは、誰でも快適にホームページを利用できるようにすることを指します。年齢や障害の有無、利用しているデバイスやネット環境に関係なく、すべての人がスムーズに情報を取得し、操作できるようにすることが目的です。
例えば、目が見えにくい人が音声読み上げソフトを使って情報を得られるようにしたり、手が不自由な人がキーボード操作だけでサイトを利用できるようにするなどの工夫が含まれます。
アクセシビリティに配慮したホームページを作ることで、より多くの人に情報を届けられ、企業やサービスの信頼性向上や機会損失の防止につながります。
アクセシビリティが求められる背景
近年、ホームページのアクセシビリティは単なる配慮ではなく、社会的な要請となりつつあります。その背景には、以下のような動きがあります。
法律やガイドラインの整備
日本では、ウェブアクセシビリティに関する法律や指針が定められています。
例えば、障害者差別解消法では、障害のある人がほかの人と同じようにホームページを利用できるようにすることが求められています。また、JIS X 8341-3:2016(高齢者・障害者配慮設計指針)では、ホームページを高齢者や障害のある人でも使いやすくするための基準が示されています。
特に自治体や大企業では、これらの指針に基づいてアクセシビリティ対応を進めています。
ユーザーの多様化
近年では、スマートフォンやタブレットを利用する人が増え、さまざまな環境でホームページを閲覧する機会が増えています。また、高齢化によりインターネットを利用する高齢者の数も増えており、音声読み上げソフトを使う視覚障害者の数も増加しています。さらに、ネット環境が不安定な状況でも快適に利用できるサイトが求められるようになっています。
ホームページのアクセシビリティを向上させるポイント
アクセシビリティを向上させるには、デザインやコーディングの工夫が不可欠です。誰もが使いやすいホームページを作るために、以下のポイントを意識しましょう。
文字の視認性を高める
テキストは適切なサイズに設定し、読みやすいフォントを選ぶことが重要です。特に、小さすぎる文字や細すぎるフォントは、高齢者や視力の弱い人にとって読みにくくなります。また、背景と文字のコントラストを十分に確保することで、視認性を向上させることができます。例えば、淡い色の背景に薄い色の文字を使うと読みにくくなるため、はっきりとした色の組み合わせを選びましょう。
音声読み上げに対応する
スクリーンリーダー(音声読み上げソフト)を利用するユーザーのために、画像には適切な代替テキスト(alt属性)を設定することが重要です。また、ボタンやリンクには具体的な説明を加え、例えば「ここをクリック」ではなく「お問い合わせフォームに進む」といった分かりやすいテキストを用いることで、音声読み上げ時にも理解しやすくなります。さらに、重要な情報を画像や動画のみに依存せず、テキストでも提供することが大切です。
キーボード操作でも利用できるようにする
マウスを使用できないユーザーのために、キーボードだけでホームページをスムーズに操作できるようにすることが求められます。特に、タブキーを使ってページ内を移動した際に、ボタンやリンクが正しい順番で選択されるようにすることが重要です。フォームの入力欄やナビゲーションメニューなども、キーボード操作のみでスムーズに利用できるかを確認しましょう。
明確な構造を持つページ設計
見出しタグ(h1~h6)を適切に使用し、情報の階層を明確にすることで、視覚的にも音声読み上げ環境でも理解しやすいホームページを作ることができます。例えば、h1をページのタイトルに使い、h2やh3を使って内容を整理することで、ユーザーが直感的に情報を探しやすくなります。また、リストや表を適切に使うことで、情報を整理し、より分かりやすく表示できます。
動画や音声コンテンツの補助情報を提供
動画には字幕やテキスト要約を添えることで、聴覚障害者や音を出せない環境のユーザーにも情報を伝えやすくなります。例えば、説明動画を提供する場合、字幕を追加するだけでなく、動画内の内容をまとめたテキストを掲載すると、さらに多くの人に利用しやすいコンテンツになります。同様に、音声コンテンツには文字起こしを併記すると、聴覚障害のある人や、音声を聞きづらい環境の人にも情報が伝わりやすくなります。
タッチ操作を考慮する
スマートフォンやタブレットでホームページを利用する人も多いため、タッチ操作のしやすさを考慮することが大切です。ボタンやリンクの間隔を適切に確保し、誤タップを防ぐようにしましょう。また、指でスクロールしやすい設計にすることで、より直感的に操作できるようになります。
自動再生や点滅する要素を避ける
動画や音楽の自動再生は、ユーザーにとってストレスとなる場合があります。特に、視覚や聴覚に障害のある人にとっては、突然の音や点滅する要素が不快に感じられることがあります。できるだけユーザーが再生を選択できるようにし、点滅するコンテンツは避けるか、制御できるように設計しましょう。
フォームの入力補助を行う
フォームを利用する際、ユーザーがスムーズに入力できるように、入力例や説明を分かりやすく記載することが大切です。また、エラーメッセージは具体的に表示し、「このフィールドは必須です」ではなく、「名前を入力してください」といった具体的な指示を示すことで、誰にとっても理解しやすくなります。
アクセシビリティ対応のメリット
ホームページのアクセシビリティを強化することは、ユーザーだけでなく企業にとっても多くの利点があります。使いやすいホームページを作ることで、より多くの人に情報を届けられるだけでなく、企業の評価向上や検索エンジン対策にもつながります。
ユーザー層の拡大
アクセシビリティを向上させることで、高齢者や障害のある人を含め、より多くの人に利用されるホームページになります。
例えば、視力が弱い人でも快適に読める文字サイズの調整機能を設けたり、音声読み上げに対応した設計にすることで、多様なユーザーが快適に利用できるようになります。
結果として、より幅広い層の人々にサービスや情報を届けることが可能になります。
SEO対策に有利
適切なHTML構造やテキスト情報を充実させることで、検索エンジンの評価が向上しやすくなります。検索エンジンは、ページの構造が整理されているサイトを好むため、見出しタグ(h1~h6)の適切な使用や、画像の代替テキスト(alt属性)の設定は、SEO対策にも有効です。また、ページの読み込み速度を速くすることで、ユーザーの滞在時間が長くなり、検索エンジンの評価が向上しやすくなります。
法令順守によるリスク回避
日本では「障害者差別解消法」や「JIS X 8341-3」などのアクセシビリティに関する法的基準が定められています。企業がこれらの基準を満たしたホームページを運営することで、法令順守の意識が高まり、訴訟リスクを回避することができます。特に公共機関や大手企業においては、法的な対応が求められるケースが増えており、今後もこの流れは加速するでしょう。
企業イメージの向上
アクセシビリティに配慮することで、社会的責任を果たす企業としての信頼性が高まります。例えば、「誰にでも使いやすいホームページ」を提供することで、ユーザーに対して配慮のある企業として認識され、ブランド価値の向上につながります。また、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として取り組むことで、社会的な評価が上がり、企業のイメージ向上にも貢献します。
ユーザー満足度とコンバージョン率の向上
アクセシビリティを強化すると、ユーザーがストレスなくホームページを利用できるようになります。例えば、ボタンのサイズを適切に設定し、タッチ操作がしやすくなることで、スマートフォン利用者の利便性が向上します。また、フォームの入力をしやすくすることで、問い合わせや購入などのコンバージョン率の向上も期待できます。使いやすいホームページは、ユーザーの満足度を高め、リピーターの増加にもつながります。
ページの読み込み速度の改善
アクセシビリティを向上させる施策の多くは、ホームページの軽量化にもつながります。例えば、不要なスクリプトを減らし、適切な画像フォーマットを使用することで、ページの読み込み速度が速くなります。これは、ユーザーの離脱率を下げるだけでなく、SEOの観点からも有利に働きます。
アクセシビリティ対応のデメリット
アクセシビリティ対応には多くのメリットがありますが、導入にはいくつかの課題もあります。対応を検討する際は、これらの点についても理解しておくことが重要です。
コストがかかる
アクセシビリティに対応するためには、通常のホームページ制作に比べて追加の設計や開発作業が必要になることがあります。例えば、音声読み上げソフトへの対応や、キーボード操作の最適化などを考慮すると、制作費用が増加する可能性があります。
特に、既存のホームページをアクセシビリティ対応に改修する場合は、新規制作よりもコストがかかることがあるため、予算計画をしっかり立てることが大切です。
制作期間が長くなる
アクセシビリティ対応を行うことで、通常のホームページ制作よりも時間がかかることがあります。
これは、各種ガイドラインへの対応や、スクリーンリーダーの動作確認、キーボード操作のテストなど、通常よりも多くの検証作業が必要になるためです。また、視覚や聴覚に障害のあるユーザーが実際に利用しやすいかどうかを確認するユーザーテストを行う場合は、さらに時間がかかることもあります。
デザインの自由度が制限される
アクセシビリティを考慮することで、デザインの自由度がある程度制限されることがあります。例えば、視認性を確保するために背景と文字のコントラストを強くする必要があったり、操作のしやすさを優先して複雑なアニメーションを避けたりすることがあります。
そのため、自由なデザインや個性的なレイアウトを希望する場合は、アクセシビリティとのバランスを取ることが求められます。
運用負担が増える
アクセシビリティ対応をしたホームページは、一度作って終わりではなく、定期的な見直しや更新作業が必要になります。
例えば、新しいデバイスやブラウザの仕様変更に対応するために調整を加える必要があったり、ガイドラインの改訂に合わせて修正を行う必要が出てきたりすることがあります。
そのため、運用を担当する人や社内のリソースを適切に確保しておくことが重要です。
アクセシビリティ対応を進める方法
ホームページのアクセシビリティを向上させるためには、制作段階から意識することが大切です。具体的な取り組みを進めることで、誰もが快適に利用できるホームページを作ることができます。
制作会社に相談する
アクセシビリティに対応したホームページを作るには、専門知識が必要になることもあります。そのため、ホームページ制作会社を選ぶ際には、アクセシビリティ対応の実績があるかを確認し、事前に要件をしっかりと伝えることが大切です。
特に、日本のJIS規格(JIS X 8341-3)や国際的なガイドラインであるWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)に準拠した設計を行っている会社であれば、安心して依頼できます。
アクセシビリティ診断を受ける
すでに運用しているホームページのアクセシビリティを改善したい場合は、専門の診断サービスを利用して問題点を把握するのも有効です。
アクセシビリティチェックツールを活用すれば、ページ内の文字サイズ、コントラスト比、キーボード操作のしやすさなど、様々な観点から自社サイトの状態を確認できます。診断結果をもとに、改善が必要な部分を特定し、優先順位をつけて対応していきましょう。
社内でアクセシビリティの意識を高める
アクセシビリティ対応を進めるためには、社内での意識向上も大切です。担当者だけでなく、デザイナーやエンジニア、コンテンツ作成者もアクセシビリティの重要性を理解し、日々の業務の中で意識することが求められます。
研修や勉強会を実施し、基本的な知識や最新のトレンドを共有することで、組織全体としてアクセシビリティ向上に取り組みやすくなります。
まとめ
ホームページのアクセシビリティは、単なる「配慮」ではなく、すべてのユーザーが快適に情報へアクセスできるようにするための「必要条件」となっています。企業にとっても、SEOやブランドイメージの向上、法令順守など多くのメリットがあります。
これからホームページを制作する企業の担当者は、制作会社選びの際にアクセシビリティ対応を考慮し、より多くの人に使いやすいウェブサイトを目指しましょう。
比較jpはホームページ制作に関する一括見積もりの比較サイトです
比較jpはホームページの制作に関する要望などを一度ご入力いただくだけで複数の業者に一括で見積もり依頼を行うことができます。
届いた見積もりや提案などを比較するだけで、制作費用はもちろん、制作スピートやデザインセンス、担当者の対応、集客に関する提案力など制作会社を様々な面から比較し探すことができます。
もちろん見積もり依頼は何度ご利用いただいても無料!
詳しくは「ホームページ制作会社を比較」のページにてご確認いただけます。
依頼実績一覧
ホームページ制作会社を検索
ホームページ制作に関するコラム
WordPressとは?無料ブログとの違い?メリット・デメリット9選
WordPressのホームページ制作相場とは?費用の内訳とコストを抑えるポイント
ポータルサイトとは?種類やメリット・デメリット、制作・運営する際の注意点
ホームページリニューアル完全ガイド|メリット・失敗する原因・手順
キュレーションサイトの仕組みとは?種類・メリット・注意点を解説
オウンドメディアとは?メリット・デメリット・成功事例まで徹底解説
ネイルサロンのホームページ制作|競合他社と差をつける要素や必要なコンテンツ
ホームページ制作会社の選び方7選|失敗しないための注意点とポイント
最低限知っておくべきアナリティクス(Analytics)の使い方(基本中の基本編)
CMSとは?CMSの種類や知っておくべきメリット・デメリット
フリーランスにホームページ制作を依頼するメリット・デメリットと費用相場を解説
ホームページ制作を外注するメリット・デメリット!費用を安く抑える方法も解説
失敗しないレンタルサーバーの選び方|料金・性能・サポートで選ぶ最適なサーバーとは?
ホームページ制作会社の種類を得意分野別・規模別・料金体系別に紹介
「格安ホームページ制作」の落とし穴!安さに隠れたリスクや注意点
アクセシビリティとは?求められる背景やメリット、デメリットについて
ホームページ制作ツール完全ガイド|初心者でも使える無料ツール13選
ホームページ制作の見積もりが高い?内訳の相場や注意点について
既存ホームページのCMS化(WordPress化)とは?メリット・デメリットについて
グループウェアと社内ポータル、社内Wiki、社内SNS、社内掲示板の違いとは?
ホームページ制作の仕様書とは?メリット・基本ポイント・注意点をわかりやすく解説
ホームページ制作の納期は?期間の目安や工程別スケジュール、短縮するコツについて
ホームページ制作契約書の基礎知識|トラブル回避に役立つ必須項目
小学校・中学校・高等学校のホームページ制作会社の選び方と制作費用相場
小学校・中学校・高等学校に強いおすすめホームページ制作会社5選
学習塾・予備校のホームページ制作の費用相場と制作会社の選び方
学習塾・予備校のホームページ制作完全ガイド|集客・費用・失敗例まで徹底解説
契約書・要求定義書・要件定義書・企画提案書・見積書・仕様書の違い
研究室ホームページの制作費用の相場と実績が豊富な制作会社6選
大学・短大ホームページの制作費用相場と制作実績が豊富な制作会社5選


ホームページ制作会社を比較できるビジネスマッチングサイト
比較jpは ホームページ制作、ECサイト制作、ランディングページ制作、スマホサイト制作、Facebookページ制作 など様々な分野について一括見積もりや資料請求依頼が無料で行えます。

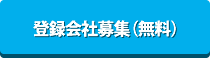
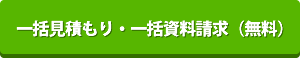

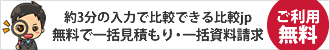
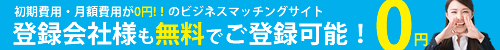




 拡大する
拡大する 拡大する
拡大する 拡大する
拡大する 拡大する
拡大する 拡大する
拡大する 拡大する
拡大する 拡大する
拡大する